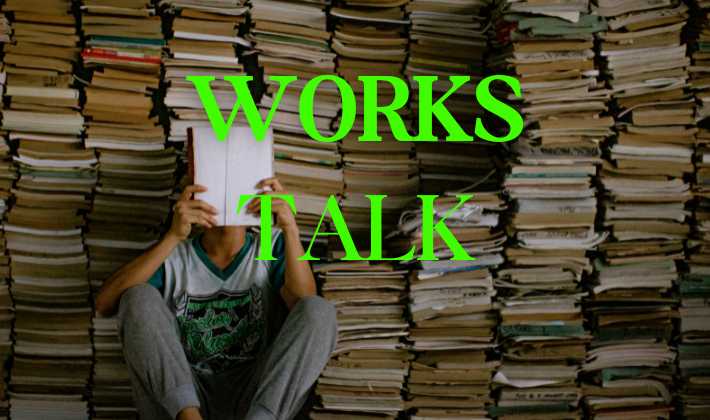こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
唐突ですが、130㎞を歩かれたご経験はありますでしょうか。
短詩系webサイト「箒」に投稿されました、柳元佑太先生の「不二曼荼羅図」。
それは単に、「不二」、つまり富士山をテーマとした作品群ではありませんでした。
自宅から歩いて、富士山を登頂してやろう、という試みの記録でもありました。
その道のりが、およそ130kmとのことです。
ページを開いて、まず目につく太字の一行。
そのたった一行を飲み込むために、しばらくの時を要したことを、強烈に記憶しています。
本文は、企画のあらましから、富士登山の歴史に軽く触れられて、動機の丁寧な説明に始まります。
そうして、写真がふんだんにあり、文献の引用もあり、要所に俳句作品があり、単調さはまったくありません。
なにより、文章が魅力的です。
もちろん、風景描写は細やかで、臨場感はたっぷりとあります。
その上で、幾度も企画を諦めるか否か葛藤されているところに、やはり引き込まれました。
むつかしい思想や言葉を用いられ、どちらかといえばシニカルな印象を受ける方。
そのような方が、130㎞歩いての富士登山を試み、ユーモアを交えつつも、やはりまじめに知的に書かれた記録です。
だいたい、どうしてそれがつまらなくなるのでしょうか。
とにもかくにも、なかなか得難いタイプの文章です。
なお、ここで1句だけ、ご紹介いたします。
星垂れて靈(たまゆら)の濃き鳥獸(とりけもの) 柳元佑太
「不二曼荼羅図」には掲句を含め、70句が並んでいます。
正直なところ、すべての作品の表現を理解し、良さを説明できるとは言えません。
ですが、〈星垂れて〉には、別格の印象を受けます。
現実の作者の動向を、制作過程をいっさい知らなかったとしても、心動かされたに違いありません。
上五から順番として、「星垂れて」に目を向けます。
星が「垂れて」と、垂れるように錯覚されるということであれば、それだけ明瞭に輝く星が想起されます。
それだけはっきり見えるのであれば、当然、星は1つではなく、明暗はありながらも、あちこちで輝いているはずです。
つまり、季語の星月夜に等しい状況であり、読者は秋の雰囲気を感じられます。
その上で、垂れる、といった表現がされています。
まるで肉体があるかのように、どろどろと、原始的なプレッシャーをこちらに放つ星々。
さながらクトルゥフ神話的な、宇宙への畏怖が感じられます。
そこに、すかさず、「靈(たまゆら)の濃き」です。
この「靈」の真字が、そのまま超自然的な力の密度の表現として、見事に機能しています。
すこし話は逸れますが、真字について、うまく消化できていないところがあります。
たとえば、蝉は、蟬とした方が、つくりの部分がまさに目があるようでふさわしいという意見には、納得できます。
ただ、文芸作品はすべて真字で発表すべきなのでしょうか。
真字による表記を表現手段の一つとして捉えるべきなのか、文芸関係者として当然のこととすべきなのか。
何を根拠に正しいとすべきか、判断しかねています。
星垂れて靈(たまゆら)の濃き鳥獸(とりけもの) 柳元佑太
作品に戻ります。
さらに、「垂れて」と、「靈(たまゆら)」の響き合いも見逃せません。
単純に、タの音が繰り返されて、韻を踏んでいることが一つです。
そこに、「靈(たまゆら)」という読みも、そのまま流体のように動く「星」のイメージに合致しています。
そうして、「鳥獸」の結びです。
強烈なまでに生き生きと描かれた命ある存在は、かえって死を連想させます。
死して、肉は土に還り、宿っていたものは、空へ。
「靈(たまゆら)」という「星」の力の、天地の循環。
飛翔できるものが置かれていることで、より、その見えないサイクルの想像を助けています。
掲句が描き出しているのは、根源的な生命の在り方です。
生きとし生けるものの尊重。
それは何ということもなく、俳句の王道です。
だからこそ、その表現の異質さ、独創性には、わくわくさせられるものがあります。
「不二曼荼羅図」では、掲句のほか、1段目の4句目、4段目の2句目と最後の句に特に惹かれます。
ぜひぜひ、「箒」をご覧ください。