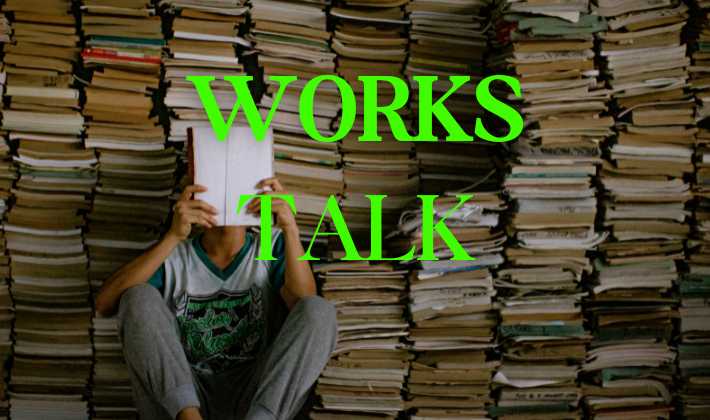こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
今回も、大見出しの同誌を買わずにはいられなかったお話の続きとなります。
さて、背表紙に掲げられているトピックスに、「俳句と短歌の10作競詠」という非常にユニークなものがあります。
ただでさえ魅力的なのですが、今回そこに稿を寄せられているのは、柳元佑太先生でした。
春や昔隕石(メテオ)が龍を鏖(みなごろし) 柳元佑太
たまたまこの動画を拝見して、本当に一瞬で、掲句とその作者名が脳に刻み込まれました。
いったい何をどうすれば、「鏖」の語を俳句の世界に持ち込むという発想に到れるのでしょうか。
ことごとく未踏なりけり冬の星 高柳克弘
高柳克弘先生のこの「未踏」もそうなのですが、あまり俳句に使われない、それでいて印象的な言葉が見事に働いている一句には、どうにも心動かされます。
「春や昔」といえば、
春や昔十五万石の城下哉 正岡子規
俳句としてはこちらがあり、
月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして 在原業平
起源として、この業平の和歌があります。
そして、「龍」こと恐竜の滅亡は約6600万年前とされています。
子規さんの明治、業平の平安の時代をぐんと抜き去って、あまりにも遥か以前の話です。
その飛躍のすさまじさが、まずユーモアを生んでいます。
そうして、「隕石」による急激な滅亡の表現として、五音が一字に凝縮された「鏖」は、鳥肌が立つほどぴったりです。
また、「鏖」の字面自体、落下した小惑星のようです。
単純に発想と表現だけを取っても、掲句には十分なおもしろさがあります。
しかし、「春や昔」の引用は、恐竜の絶滅を印象深くするほか、何の効果も果たしていないのでしょうか。
一度、子規句に立ち戻ります。
「春や昔」は、季節をひねりなく素朴に示し、字余りでしかもア段の音が多いと、すでに明るく駘蕩とした雰囲気を表出しています。
それに、「城下」と続き、高さと広さが一度に想像され、結びも「哉」とゆったりしています。
一句の雰囲気はしっかりと、のびやかなものに統一されています。
一方で、業平歌です。
「月やあらぬ春や昔の春ならぬ」の「や」を反語とするか疑問の語とするかなど、解釈が分かれる作品ではあります。
ただ、いずれにせよ、「わが身ひとつはもとの身にして」までの強い違和感の表明には、人間の深い嘆きがあります。
春や昔隕石(メテオ)が龍を鏖(みなごろし) 柳元佑太
それらのことを踏まえ、掲句を見直します。
すると、子規句の、そもそもすこし過剰なのんびりしたムード。
業平歌の、鬱屈としながらもそれが極限まで美に高められた雅な空気感。
そのどちらにも心を落ち着けられず、人がいない世の大量絶滅を幻視する、作中主体が浮かび上がってきます。
一見すると、あまりにも尋常ではない憂鬱さです。
しかし、ここで効いてくるのが、「隕石」としてメテオと読ませ、恐竜を「龍」とする表現です。
これだけの知的操作を行う気力があれば、間違いなく本当の絶望ではないでしょう。
むしろ幾ばくかの喜ばしさもあり、この幻視によって、憂鬱を乗り越えている印象すらあります。
ネガティブな感情が捉えたネガティブなイメージを詩に換え、回復する作中主体を描くこと。
掲句はさながら虚数のような、特異な詩情で満ちています。
このように、今後どういう俳句を切り拓くのかまったく未知数で、大注目の作家です。
「俳句と短歌の10作競詠」の10句も、その型破りのほどが驚異的で、まずそこに大きく手を叩きたくなりました。
5句目までは(なんのこっちゃ・・・・・・?)と戸惑っていました。
しかし、6句目での連作のテーマの種明かしに、(え、えっ・・・・・・うそん、そういうこと!?)と、気づけば笑っていました。
最も好きな作品は2句目です。その次はとなれば、9句目を挙げます。
2句目は、上五の字余りと字面同士の響き合いによって、作品世界の雰囲気がより印象深いものとなっています。
ページが変わって、400字弱の散文が続きます。
一行目からしてユーモラスで、(いや、ちょっと待ってぇな)と、思わずツッコミたくなるほどです。
しばらくは硬めの文体で、堅苦しさとは対極の話題をつづられていて、そのちぐはぐさがおもしろく引き込まれます。
しかし、途中から、はっとさせられる論が提示されます。
そうして明かされるのが、今回の大胆な連作の動機です。
単なる思い付きではなく、しっかりとした意図があっての、実験的な試みであることが示されます。
ここからも、新しさへの強い意志と、実際に新しい手法を創出する技量がうかがえます。
次に登場される総合誌では、どのような試行をなさるのでしょうか。
新作の発表が、心待ちにされます。