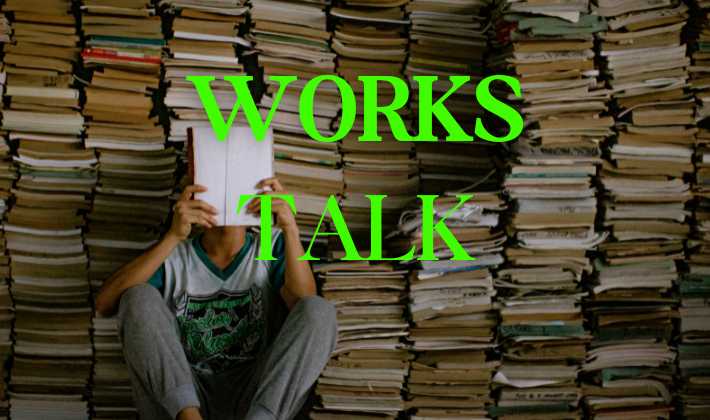こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
大見出しの同誌は、買うという選択肢しか浮かびませんでした。
インターネット上のページで目次を一見した際は、思わず声が出ました。
それくらい、惹かれる執筆者揃いだったお話の続きをいたします。
さて、特集は、「なぜ、俳句なのか――私が俳句を選んだ理由」と題されたものです。
その寄稿者の一人に、岩田奎先生がいらっしゃいます。
にはとりの歩いてゐたる木賊かな 岩田奎
2022年にふらんす堂さんより出版された第一句集、『膚』に収録されています。
掲句は、いかがでしょうか。
なんとなく、詩的で良いような印象はあります。
ただ、その良さを具体的に言葉にしてくれと頼まれると、なかなか難儀で困ってしまうのではないでしょうか。
たとえば、岩田奎先生は波多野爽波(1923~1991)という俳人を敬愛されています。
2022年に暁光堂さんより出版の『波多野爽波俳句全集』の、補遺の選をされているほどです。(補遺とは、句集には収録されていない作品の中より、何かに収録されて活字になったものを言います)
鳥の巣に鳥が入つてゆくところ
波多野爽波の著名な作品の一つがこちらです。
鳥の動作だけが、何も難しくない言葉で表現されています。
それだけに、魅力を説明する以前に、そもそも良いか悪いかを判断すること自体、困難を伴いそうです。
ここで、経歴に触れますと、波多野爽波は高浜虚子の晩年の弟子です。
そして、高浜虚子が十代の頃から俳句を学んだのが、正岡子規です。
正岡子規と言えば、西洋絵画的な写生を提唱することで俳句の革新を成し遂げた、いわば写生の祖です。
波多野爽波はこのような系譜にあり、当然のこととして、写生に徹した俳人です。
原点に立ち返りますと、写生は、着想の陳腐さに無頓着な当時の俳諧を、新鮮で文学的な価値を有する俳句とするための方策でした。
その際、邪魔になってくるのが先入観です。
固定観念にとらわれた散文的とも言える日常生活的な物の見方から脱して、俳人として韻文的に対象に迫るにはどうすれば良いのでしょうか。
そこで、波多野爽波が提唱したのが、「俳句スポーツ説」というもので、俳句作品を多く読んで多く覚え、同時に、多く作って多く捨てることを至上とされました。
波多野爽波は自説をたゆまず実践し、試合中のアスリートのように、頭が働く前に反射的に、眼前のものを写生して句にすることを突き詰めました。
そうして、人間の認知が極限まで削がれた、本来的な世界そのものに極度に近い、ありのままの現実の様相を提示することに到りました。
にはとりの歩いてゐたる木賊かな 岩田奎
岩田奎先生の掲句も、波多野爽波の影響下にあってむき出しの現実を提示することを志向し、その成功の是非を読者に委ねたものとして捉えることは可能です。
また、「木賊」は研ぐ草でもあります。
めん鶏ら砂浴び居たれひつそりと剃刀研人は過ぎ行きにけり 斎藤茂吉
1913年に東雲堂書店さんより出版された第一歌集『赤光』収録の、斎藤茂吉の作品です。
鶏と、研ぐことに関連する要素、現場を去り行く存在の登場が、共通しています。
〈にはとりの〉を、茂吉作品の本歌取りではないとするのは、むしろ不自然なくらいです。
そのため、掲句は、知的構成の巧みさが魅力の作品だとも言えます。
しかし、これら二つのことが、作品の価値のすべてでしょうか。
ただ波多野爽波や斎藤茂吉をなぞっての、いわば再生産のような創作など、どうしようもなくさびしいばかりです。
にはとりの歩いてゐたる木賊かな 岩田奎
めん鶏ら砂浴び居たれひつそりと剃刀研人は過ぎ行きにけり 斎藤茂吉
再掲し、より踏み込んで両者を比較いたします。
茂吉歌では「めん鶏」も「剃刀砥人」も動いています。
一方で、〈にはとりの〉では、「にはとり」のみが動いています。
このうち動かないものに設定されているのは「木賊」。まっすぐに縦に伸びる植物です。
そして、「にはとり」は鳥類でありながら飛べず、生活が地上に限られており、空へ、つまり上方向へは移動できないことが強く意識される生き物です。
動きが横軸に限定された「にはとり」に対し、「木賊」が基準点のように存在していることで、ここに空間性が発生しています。
さらに、夜明けと共に鳴く「にはとり」は、太陽の象徴として神聖視されるものであり、時間を暗示させるものでもあります。
そこに、刃物を連想させる「木賊」があり、屠殺される「にはとり」のイメージが喚起されます。
空間と時間。太陽と生と、夜と死と。
一句は、世界そのものが不用意に見せてしまった韻文的な裂け目から、不可視のはずの根源的様相を抉り出し、具象的に描くことを成しています。
これらのことから、世界の原形を捉え、提示することを糸口として、よりその奥の、世界のシステム自体にまでも、手を伸ばそうとしている作家として、岩田奎先生は捉えられそうです。
さて、本題の、「俳句四季」8月号に戻ります。
まず、エッセイのタイトルからして、俳句を始めた理由とどう結びつくのか見当がつかず、興味を惹かれました。
本文の文字数は1000字強。のっけから身も蓋もない書きぶりがおもしろく、早々に(ふはっ、さすがぁ・・・・・・)となりました。
それから、ラッパーたちが即興のラップで勝負する、MCバトルと呼ばれるものに触れられます。
たとえば、このようなものです。
岩田奎先生とはそう歳が離れていないため、流行のほどは実際に体感しています。
高校生だった頃、クラスの目立つ人たちがこぞって「テングノハナッ! テングノハナッ!」と首を振っていたことを覚えています。(もちろん、他のラッパーたちのラップも数多く真似されていました)
なかには、MCバトルの動画を視聴するため、授業中だろうと教師にトイレに行きたいと言い、席を外す生徒もいました。それくらい、みんな熱狂していました。
二段落目からは、俳句甲子園のことがより掘り下げられてゆきます。
ここでもきっちりとお話にオチをつけられていて、クスリとしてしまいます。
気づけば(出身どこよ・・・・・・?)と大阪人か否かGoogleで検索をかけていました。
読者サービスの手厚い、つくづく退屈しない文章です。
しかし、ひと笑いさせてくれた後、真剣な問題提起が行われます。
おそらくは初出の実体験を語られ、自身に引き付けながら、現代の空気感を表す事例を提示されます。
そして、結びです。
終わり良ければすべてよし、とも言われますが、最後は短いながらも印象的な言い回しをされて、文章は締めくくられます。
その切れ味も見事で、まさに読み応え抜群のエッセイでした。