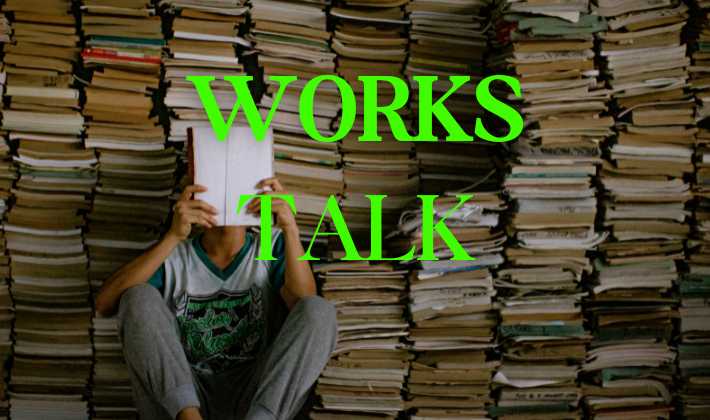こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
毎月欠かさず、購入する俳句の総合誌がある方は、どれほどいらっしゃるのでしょうか。
やはり買いだしてしまうとキリがなく、部屋のスペースにも限りがあります。(かと言っていつか紐でふん縛って外に出すというのも、なかなか忍びないものです)
そのため、どうにも惹かれるトピックスがあった場合に、衝動に駆られて買うものという心持ちがあります。
そして、「俳句四季」の2025年8月号が、まさにそれでした。
東京四季出版さんのサイトで目次を見てすぐ「おっ・・・・・・ふぉっ・・・・・・」と、思わず声が出ました。
まず、「今月の華」に森賀まり先生です。以前に二度ほど、句会をご一緒させていただき、大変お世話になりました。
同コーナーでは、俳句作品に続いて、箱根旅行の思い出を語られています。
エッセイは800字弱のものです。ただ、すさまじい読み応えでした。
冒頭のあたりは明るく、ふふっと笑ってしまう楽しさがあります。
そうして、箱根での話になります。
ここでは旅の現実的な部分がフォーカスされていて、その空気感がよく分かります。
旅行中における共感しやすい事態があっさりとした調子で語られるため、非常に引き込まれました。
それから、お話はすこし(人によってはすごく、かもしれません)切なくなってきます。
言うまでもなく、記憶の世界の輪郭は、ぼやけゆくものです。
そこに、レコードをかけるように、田中裕明の一句が引用されます。
田中裕明は森賀まり先生の旦那様です。ただ、もうこの世にはいらっしゃいません。
小さいために多くは語れませんが、それでも確かに存在してくれるもの。
小さいからこそ完全な形で、いつでもこのように思い出せるもの。
それが、俳句です。
ここから文章は切ないだけでなく、記憶するということの美しさが捉えられた、詩的なものになってゆきます。
大切な思い出が、大切であるがゆえに生まれる錯覚。
その豊かな誤読は、どうしようもなく強い想いを伝えてくれます。
エッセイの結びにうながされるまま、俳句作品に立ち戻りますと、言葉にし難い詩情が目に見える形で表されていることがより深々と読み取れ、格別に感動的です。
さて、せっかくですので、もう少し、森賀まり先生のことをお伝えしたいです。
句集は『しみづあたたかをふくむ』が、最新のものです。
出版は2022年、ふらんす堂さんからです。同句集は電子書籍化もされております。
草の蜘蛛ふはりと何もなき方へ
掲句には「何もなき方」、つまり虚を見つめる視線がありますが、これは、
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ 藤原定家
であったり、
花は散りてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる 式子内親王
といった、新古今和歌集の美学に通ずるものがあります。
正岡子規は西洋美術的な写生の考えを提唱し、同時に万葉集を称揚して、明治期に俳句革新を成し遂げました。
そのため、万葉集を尊ぶ流れは、俳句の世界に脈々と続きます。
当然のことですが、それ自体はまったく問題ではありません。
しかし、だからこそ、新古今的な、新たな流れにある掲句には大変な魅力があります。
ただ、新古今和歌集というと、修辞の巧みさがすさまじく、象徴的で幽玄といった、取っつきにくいイメージがあるかもしれません。
一方で、『しみづあたたかをふくむ』の題には、一見して明るく、やさしい印象をお受けになるのではないでしょうか。
春風に背中ふくらみつつ行けり
好きな人なれば声浮く五月かな
セーターの毛玉仕方のなき人よ
同句集には、まさにその通りの、楽しい雰囲気の作品ももちろん収録されています。
この、作品の振り幅の広さこそ、俳句のプロの凄さです。
「俳句四季」2025年8月号も、「しみづあたたかをふくむ」も、ぜひぜひチェックしていただけますと幸いです。
また、こちらからは森賀まり先生の略歴に触れられます。
昼蛙どの畔のどこ曲らうか 石川桂郎
そして、演題の石川桂郎は、軽妙な秀句を数多く作られ、お酒を愛された大変魅力的な人物です。
そのまま石川桂郎についてお知りいただけますと、これまた幸いです。