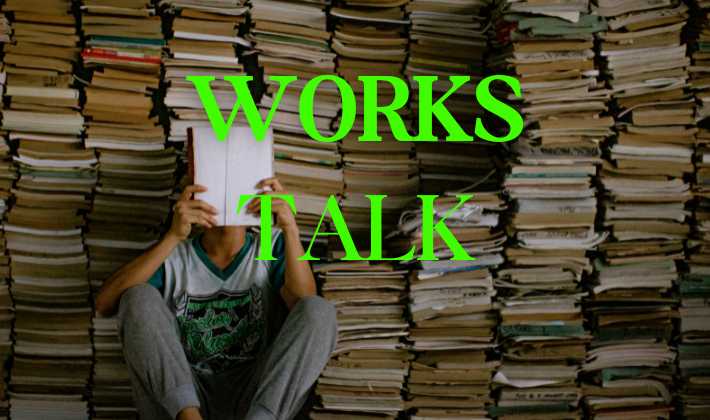こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
唐突で恐縮ですが、梅田の紀伊国屋書店さんに感謝申し上げたいです。
と申しますのも、ブログを始めるにあたり、(小澤實先生のことは書かななぁ・・・・・・)と、その著作を得るべく出かけたのですが、梅田の紀伊国屋書店さんの品揃えの良さには、ただただ度肝を抜かれました。さすがでした。
まず、スクラムでも組むかのように、ぼんぼんと置かれている分厚い歳時記。
さらに分厚くインパクト十分な『山頭火全集』の1から4巻。
それから、書棚の一段にずらっと並ぶ、ふらんす堂書店さんの『○○の百句』シリーズ。
そして、最新の俳人協会新人賞を受賞された桐山太志さんの『耳成』など、句集がよりどりみどりで、(やっぱ都会すごぉ・・・・・・)と思わずにはいられませんでした。
さて、『瓦礫抄』はふらんす堂さんより、2022年に出版された「俳句日記」です。
同著はまさに「日記」で、まず日付と曜日、天気の記載があり、作品が1句置かれ、100字ほどの散文が続くというひとまとまりが1年分、(閏年のため)366回繰り返される構成となっています。
収録期間は2011年12月1日から、2012年の11月30日までで、言うまでもないことですが、2011年は3月11日に東日本大震災が発生した年です。
そのため、帯にも、あとがきからの抜粋として、『「瓦礫抄」なる題名は、震災の瓦礫による。震災後の心細さを忘れてはならじと、題とした』とあります。
そうして、
春の星拳ふたつをひらきえず
が、同じく帯に、3月11日の句として掲げられています。
今回はこの句から、話を進めてゆきたいです。
まず、中七下五に対して、春以外の季節の星では、作品の印象はどう変わるでしょうか。
春のつぎの「夏の星」ですと、暑い地上とは離れた世界として涼しさが感じられ、また、美しくロマンチックなイメージが浮かびます。
そのため、「拳」を強く握りしめているような緊張した状況とはちぐはぐで、違和感しかなく、感動も何もありません。
同様に「秋の星」でも、澄んだ空の心地よいイメージや、そもそもの秋が持つ繊細な情趣に、「拳ふたつをひらきえず」のこわばった状態はやはり合わないです。
「冬の星」となりますと、これは「凍星」や「星凍つる」の語があり、「ひらきえず」の感覚と響き合うため、作品としてありえないとまでは言えなさそうです。
しかし、「星」が凍りついたように感じられて、自分の「拳」も凍ったかのように開けられない、というのは、連想として密接であまり驚きが少なく、詩情豊かとは言い難いです。
よって、あらためて、『春の星』のすばらしさがよく分かります。
厳しい冬を経ての春ですから、『春の星』からは優しさ、あたたかさが感じられます。
しかし、同時に、潤んで見える不確かなものでもあります。
掲句に添えられた短文には、「人間は心細くささやかな存在にすぎない。それを忘れてはならない」とあります。
たいていの場合、心穏やかにしてくれるはずの『春の星』に相対して、そのあやふやさが今は気になってしまう。
自身の存在を確固たるものとして、たとえそれが錯覚だとしても感じたく、ひたに握りしめる両手。
上五を「や」で切らないところや、「ふたつをひらきえず」のひらがな表記にも、不安さがにじみ出ています。
大震災より1年後の句として、まさに万感が込められた一句です。
ここから、すこし『瓦礫抄』から離れるのですが、同じく「春の星」が季語の、一読して覚えてしまった作品に、
妻の遺品ならざるはなし春星も 右城暮石
が、あります。
上五の字余りから、亡くなってしまった『妻』へのあふれんばかりの想いが感じられて、胸がきゅっとなります。
上五は『遺品』で、中七は『なし』と、助詞ではないため言葉が繋がらず、全体として語がブツブツと切れる韻律となっているのも、痛切な悲しみに喘ぎ苦しんでいるイメージが浮かんでしまいます。
誰かが何気なく見ている星は、ほかの誰かにとっては大変に思い出深いものだという観点は、私に大きな学びを与えてくれました。
私にとって俳句は、見飽きた日常をパッと新鮮なおもしろいものにできる素敵な文芸です。
そのため、『俳句カフェをやりたい』などと言って、俳句が流行ることを願っております。
暮石の作品は、「おもしろい」とするのは憚られますが、俳句の可能性を強く感じさせます。
一方で、これは季節が変わりますが、もう一つご紹介したい作品があります。
ことごとく未踏なりけり冬の星 高柳克弘
『未踏』なんて、俳句に使われているのを目にしたのはこれが初めてでした。本当に格好いい作品です。
ただ、夜空の星がみんな『未踏』なのは当たり前で、当たり前のことを格好良く言っているだけではないか、という批判もあったそうです。
この当たり前、ということを考えるとき、すぐに浮かぶのが、
一月の川一月の谷の中 飯田龍太
この作品です。
言っていることは難しくないどころか当たり前で、これが超有名な俳句だと言われると、当惑される方もいらっしゃるはずです。
なお、俳句の世界では、いわゆる「ただごと俳句」と呼ばれ、
いや、当たり前やん、であったり、ただの報告やん、などと指摘され、忌み嫌われる作品の傾向があります。
もちろん、今しがた例示した2句は、批判も皆無ではありませんが、少なくとも、万人に「ただごと俳句」として切って捨てられた作品ではありません。
「ただごと俳句」のギリギリに遊ぶのではなくて、正面から当たり前のことを――「ただごと」を言っていながら、しかし、認める人もいるような作品。そうしたものに、なにか俳句の新しい可能性があるのではないかと、気になっています。