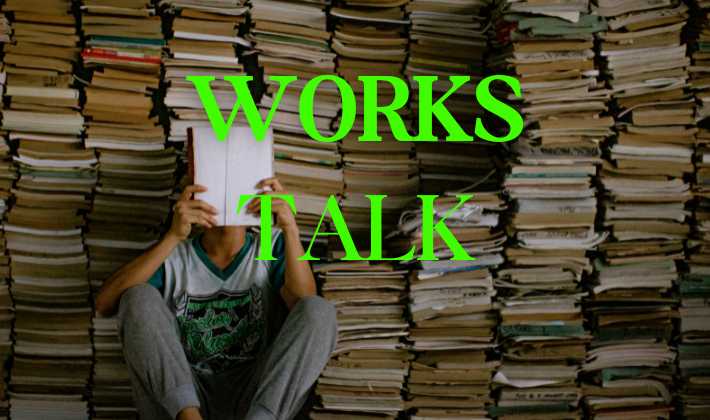こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
そういえば、当ブログ名に含まれる「日乗」について、いや、「日乗」ってなにさ、とお思いではないでしょうか。
広辞苑には、(「乗」は記録の意)日記。
と、あります。
とはいえ、「日乗」は、何かの折に目に付き、物珍しく感じて用いたわけではなく、今回ご紹介いたします作家の、その著作を念頭に置き、倣ったものです。
それが、永井荷風(1879~1959)であり、『断腸亭日乗』です。
つまるところ、荷風さんリスペクトというわけです。
久保田万太郎の俳句に惹かれ、それから万太郎が永井荷風の『すみだ川』を愛読していたことを知って、荷風さんに興味を持ちました。
なお、荷風さんという呼び方は、半藤一利著『荷風さんの昭和』の影響です。
同著はそれくらい興味深く学びのあるものでした。文庫本にもなっておりますので、ぜひチェックしていただければ幸いです。
さて、端的に申しますと、荷風さんの最大の魅力は、粋の体現者たるところです。
九鬼周造曰く、粋とは媚態、意気地、諦めの三要素で構成されます。
それぞれはざっくりと、女性への興味、心の強さ、執着の無さ、と換言できます。
まず、荷風さんは芸者や女給、踊り子たちを描いた作家です。一番目は言わずもがなといったところです。
そして、意気地。心の強さのほどは、『断腸亭日乗』の記述に触れていただければ一目瞭然です。
「日本現代の禍根は政党の腐敗と軍人の過激思想と国民の自覚なきことの三事なり。政党の腐敗も軍人の暴行もこれを要するに一般国民の自覚に乏しきに起因するなり」
昭和11年2月14日の記述の抜粋です。
荷風さんは戦争へ突き進む日本全体の熱狂にも惑わされず、批評精神を堅持し続けました。
その態度は冷静さを保ったというより、もはやこわいくらいに、ひたすら冷め切ったものでした。
最後の諦め、執着の無さは、『妾宅』をご一読いただきたいです。
「しかし人間は総じて男女の別なく、いかほど正しい当然な事でも、それをば正当なりと自分からは主張せずに出しゃばらずに、何処までも遠慮深くおとなしくしている方がかえって奥床しく美しくはあるまいか」
なかでも取っ付きやすそうな一文の抜粋です。
同作はほとんど随筆的な小説で、筋らしい筋もありません。荷風さんが本心を述べていると捉えても、そう的外れではないはずです。
粋は、日本独自の感性だと、九鬼周造は言っています。
荷風さんはその粋という、日本人に根差した美意識に忠実に生きた作家です。
著作権も切れております。ぜひぜひ一度チェックしていただけますと幸いです。
具体的な作品といたしましては、『夏の町』や『雪の日』、『勲章』は短くおすすめです。
『すみだ川』と並ぶか、それ以上の傑作ともされる作品に『濹東綺譚』があります。
こちらは映画化されており、Amazonでも視聴が可能です。
そして、俳句です。
紫陽花や身を持ちくづす庵の主
梅雨の頃の暗く湿った空気感に、「紫陽花」は枯れるとなれば、散ることも落ちることもなく、ただ色褪せて朽ちてゆきます。
衰えをまざまざと見せつけるかのような花と、生活をどんどんと乱しゆく人間。
一句は退廃的な雰囲気で統一され、言葉と言葉が見事に響き合っています。
これが荷風さんの作品となればなおさら、生き様の象徴のように思えておもしろく、忘れがたい秀句です。
長らへてわれもこの世を冬の蠅
こちらは蕉門の宝井其角の、
憎まれてながらへる人冬の蠅
を、念頭に作った句とされています。
其角は豪放磊落な性格で、粋人の極みともされ、江戸っ子に大人気でした。
まさに荷風さん好みの俳諧師で、その随筆集に『冬の蠅』と名付けているくらいです。
掲句に戻りますと、汚いものにたかる不浄な生き物に自らをなぞらえ、滑稽さを演出しながらも、どこかしぶとさを誇っているような趣があります。
哀れさとユーモラスさが巧みに表現されており、俳諧味の濃い素晴らしい作品です。
小説も随筆も一級品で、俳句も作れる。
芸達者で粋な永井荷風を、ぜひぜひ好きになっていただけますと幸いです。