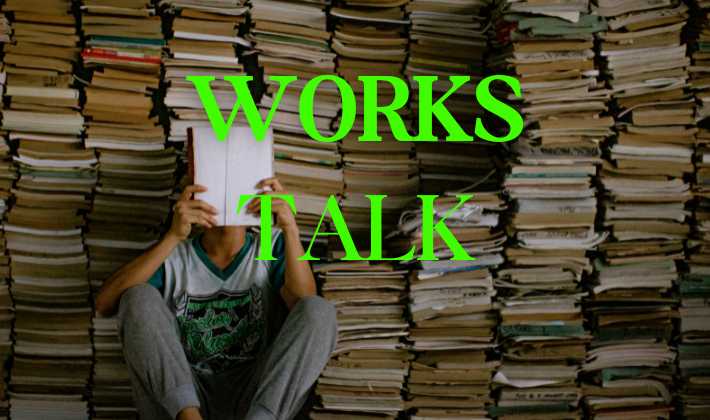こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
桜また来るから桜忘れていい 佐藤文香
帯文掲載の作品でなくて恐縮ですが、集中もっともこの句に惹かれました。
さて、『菊は雪』は、藤井あかり著『メゾティント』と一緒に、やはりその白と黒の装丁の美しさに惹かれ、購入いたしました。
出版は2021年、左右社さんからです。
これはどちらが良いという話ではありませんが、『メゾティント』は帯が無く、あとがきも3行のみと、これまで私が触れた句集の中で飛びぬけて潔い印象の句集でした。
一方で、『菊は雪』は白地の大きな帯があり、その帯文で「句集制作ドキュメンタリー」と銘打たれた「菊雪日記」という文章が、巻末に収録されています。
この紹介文を一目見て、(えっ、ええ・・・・・・ええん・・・・・・?)とかなり戸惑いました。
もちろん、公開を前提とした日記です。すべてを鵜呑みにはできませんが、それでも、作家が自身の工房を明かしてくれるようなものです。
話題は第1、第2句集を制作されていた際の心情や、その振り返りにも及びます。
大盤振る舞いといいますか、大サービスに他なりません。
ただ、どうしてこのような試みをされたのかについては、その1ページ目に早々と示してくださっています。
そして、インターネット上の『菊は雪』販売ページにおける内容紹介の項で引用されている「菊雪日記」の一節に、
「何のために俳句を書いているかと聞かれたら、俳句ができることの拡張のためだとこたえる。先人が既に耕したことのある土地だとしても、今自分が耕し直すことには意味があると思いたい」
と、あり、作句信条が明確に表明されています。
当然、重要でない部分などありませんが、その上で、「耕し直す」という表現が導き出されていることが、特に注視すべきポイントではないでしょうか。
このような創作の姿勢を踏まえながら、冒頭の作品に立ち入ってゆきます。
桜また来るから桜忘れていい 佐藤文香
「桜」の木があり、「また来る」ことを決めているため、目の前のこの「桜」のことは「忘れていい」と思う。
と、言葉の意味だけを見つめ、ひたすらに散文的に理解するなら、こうなります。
しかし、言葉の持つ情趣や韻律ということに目を向けますと、まず、「桜」の繰り返しが意識されます。
「桜」は日本人の心の花とも表現され、雪と月に並んで美しいもの代表とされるものです。
その「桜」を執着心を表すように二度も用いながらの、字余りの「忘れていい」は、もう、感情があふれてしまっているとしか考えられません。
ただただ、「桜」のあまりの見事さがもはや苦しく、「忘れていい」、と、自らにそう言い聞かせている作中主体の姿ばかりが想像されます。
そうして、掲句の構造にもうすこし立ち入りますと、「桜」の語が繰り返され、「また来るから」という行動の繰り返しの予告があり、それから、「忘れていい」の裏腹の本心の表現があります。
反復し、ひっくり返すということは、まさしく鍬を振るい、「耕し直す」営みと繋がる印象があります。
ですが、決して、掲句が著者の作家性を、端的に象徴した作品であるなどと解していただきたいわけではありません。
ここでわずかな間、作品から離れ、『菊は雪』の構成に触れたいです。
同著には2015年から2021年の550句が収録されており、その章は32に分かれます。そして、句集としては稀なことに、散文付きの句群の存在があります。
細かな章立てと、ごく短いエッセイの挿入に、「菊雪日記」の収録。
これらのことからは、試行を絶え間なく繰り返され、そして、大きな価値が無い(と判断された)慣習は実際に乗り越えてしまうという、著者の高い革新性がうかがえます。
一方で、それゆえに、その作家性を掴むことは、少なくとも容易ではありません。
桜また来るから桜忘れていい 佐藤文香
忘れられないことを、「忘れていい」と言って覆すこと。そうして、大胆に新しくすること。
つまるところ、掲句が取っ付きやすく教えてくれているのは、佐藤文香俳句の魅力に他なりません。
なお、革新性については、「菊雪日記」の1月24日に、類似したことを著者自身の語で、話題にされています。
当然ながら、そちらのほうが表現が断然おもしろいです。
『菊は雪』は電子書籍にもなっております。ぜひぜひご購入をご検討いただけますと幸いです。