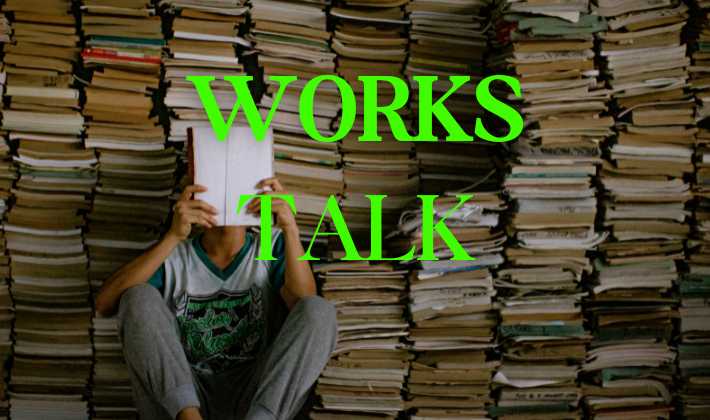こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!
花冷の鏡の美容師に応ふ 藤井あかり
先に述べておきます。集中もっとも惹かれた作品が掲句です。
『メゾティント』は2024年に、ふらんす堂さんから出版されています。
先日、書店の俳句コーナーを眺めていて、装丁のあまりの美しさに迷わず購入を決めました。
白と黒のシンプルですっきりしたデザインが、非常に印象的でした。
魅力的な黒の使われ方、という意味合いで、(単に私が最も好きな画家のためかもしれませんが)マネの絵画が連想され、とても興奮しました。
マネはティッツァーノなどの過去の名作を踏襲しながら、「現代の古典」、あるいは現代で古典を創作しようとした画家です。
むかしに学んで現代を描くこと。それは私が俳句作家として常に念頭にあることです。そのためマネのことは大変に尊敬しております。
表紙からして、『メゾティント』にも現代性が描かれていることを期待しておりました。そして、最高でした。
ただ、『メゾティント』の意味はすみません、パッと分からなかったです。
白黒二色の鍵盤のような表紙につられて、(メゾゆうたらメゾピアノとか、メゾフォルテとかゆうし、たぶん音楽用語なんかな・・・・・・?)と勘違いを起こしておりました。
言葉としてのメゾティントは、百科事典マイペディアによると、
「銅版画技法の一つ。凹版の一種で,版面をのこぎり歯状のロッカーで縦横にひっかいて無数の線を作ったのち,この線の凸部をつぶして図柄を出す。つぶされた部分はインキが付かないため白く浮かび上がる。微妙な明暗の変化が得られ,絵画的効果に富む。17世紀中ごろドイツで発明され,18―19世紀の英国で特に盛んに制作された。日本では長谷川潔,浜口陽三が有名」
とあります。このうち、「微妙な明暗の変化」は句集を読み解くキーワードに思えてなりません。
さて、冒頭に掲出した作品に戻ります。
花冷の鏡の美容師に応ふ 藤井あかり
まず、「花冷」。花、つまり桜が咲くころ、急にそれまでのあたたかさが一転して、感じるさむさのことです。
もう、語そのものが抜群に美しいです。
だからこそ、その美にやられてしまって、作品が綺麗になりすぎて現実感に乏しく、嘘のように思えて感動し難いものになりがちな、むつかしい季語ではないでしょうか。
しかしながら、掲句はリアリティある日常の1コマを淡々と描きつつも、「花冷」の情趣がたっぷりと感じられる作品となっています。
昔から雪月花、というように、「花冷」の花は、美しいものの三大巨頭の一つです。
そして、「美容師」がいる、つまり美容院は、言うまでもなく髪を綺麗に整えて、美しくなるための場所です。
ここでまず、花と美容室が美という共通項で結ばれ、詩的な響き合いを生んでいます。
加えて、「花冷」の寒さ、硬質なイメージは、美容室の「鏡」であり、ハサミと響き合います。
その上で、単に美容師、ではなく、「鏡の美容師」としているところに注目されます。
前述の通り、「花冷」とは桜が咲いて、華やかなイメージが湧くころの、現実としての意外な寒さのことです。
その意外さ、違和感が、そのまま「鏡の美容師」のフレーズで描き出されています。
日常において、鏡の前に立っているときに、人に後ろに立たれること自体そうそうありません。まして、話しかけられることもそうないですし、それで返事をするにあたり、振り返ってその人の顔を直接見ることなく、前を向いたまま、鏡像に話すように返事をすることなどとても考えられません。
しかし、美容師であれば、その考えられない異常なことが当然のこととなります。
韻律に着目しても、「美容師」が語割れを起こしており、そこから、強い、と言ってもよさそうなほど違和感を、作中主体が、現状において抱えていることが読み取れます。
この表現を選び取っているところから、作者の鋭く、繊細な感性のほどを想像してしまうのは読みすぎでしょうか。
そして、さきほど、メゾティントの意味に触れるに際し、「微妙な明暗の変化」のフレーズに目を向けていただきました。
「花冷」の、花と冷は、まさに明と暗とも言い換えられそうです。
花冷の鏡の美容師に応ふ 藤井あかり
掲句は書籍紹介における「作品紹介」の句群にも含まれておらず、また、鑑賞文も私には見つけられませんでした。
しかし、『メゾティント』と照応する秀作であることは間違いありません。
同著は、このようなぞくりとする新鮮な作品でいっぱいです。
ぜひぜひご購入をご検討いただけますと幸いです。